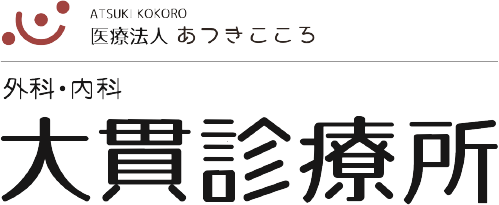孤独死もまた良し
私の祖母は「孤独死」をした。
今から15年前の夏の日。医師になってまだ3ヶ月の私に、祖母の異変を伝える電話が入った。急いで祖母宅に着くと、そこには布団の中で冷たくなり、変わり果てた姿の祖母がいた。
母によると、前日の夜は普段通り電話で話をしたとのことだった。ちょうど花火大会の夜。「家から花火がきれいに見えるよ」が最後の言葉になった。翌日祖母宅を訪ねたところ応答がなく、室内に入ってみたらすでに息をしていなかったとのことだった。検死の結果、死亡推定時刻は当日早朝とされた。
私は、完全に「おばあちゃん子」であった。「お医者さんは人の役に立つ素晴らしい職業だよ」と幼いころから刷り込まれてしまい、その期待に応えようとして医師になったと言っても過言ではない。野口英世の伝記を買ってきては「読書百遍意自ずから通ず」と教えてくれたり、私が悪いことをした時は「天知る地知る己知る」「公明正大に生きよ」と言って諫めてくれた。厳しい面はあったが、それ以上に深く深く愛してくれた。
そんな祖母に、亡くなる数年前から異変が現れた。1日に何回も電話を掛けてくるようになった。同じ話を何度も何度も繰り返す。近所のスーパーに財布を持たずに買い物に行く。お風呂に入りたがらない。散歩に出ては帰り道が分からなくなる。ある時は大塚台から大工町まで歩いて行ったのを迎えに行ったこともあった。当時はまだ認知症という言葉はなく、「痴呆」や「ボケ」と言った。私は、大好きな祖母がボケていく姿を受け入れられず、動揺し、そして苛立った。時には激しい言葉も浴びせた。そして自己嫌悪に陥った。
そろそろ一人暮らしは無理なのでは・・・と話し合っていた矢先、祖母はあっけなくこの世を去ってしまった。医師として祖母の最期を看取りたいと思っていたが、結局何の役にも立たなかった。最期の瞬間に誰も立ち会わず、たった1人で旅立たせてしまった。己を責め、後悔し、そして祖母に謝罪した。「こんなに寂しくみじめな最期はない」と思った。
その後、たくさんの患者さんの最期に立ち会い、看取りの経験を重ねるうちに、私の気持ちも徐々に変わって来た。それは、「祖母は祖母らしい最期だったかもしれない」ということである。もしあのまま生きていたら、きっと認知症や介護の問題がより切実になっていただろう。プライドの高かった祖母は、私達に世話を掛ける前に潔くこの世を去ったのかもしれない、と思えるようになってきた。
壮絶な闘病の末に亡くなる人、「死にたくない」ともがきながら亡くなる人、天涯孤独でひっそりと生涯を終える人、多くの家族に見守られ大往生を遂げる人。様々な最期があるが、大切なのはそこに「その人らしさ」があるかどうかだと思う。その人らしい最期だったかどうかを決めるのは、遺された者の気持ちである。そしてその気持ちは、数年をかけて少しずつ変化していくのだ。
祖母は祖母らしい最期を遂げた。その意味では「孤独死もまた良し」である。今は祖母が口癖のように言っていた「あなたの顔を見ただけで患者が半分病気が治ったような気持ちになるお医者さんを目指しなさい」という言葉を噛みしめている。
祖母は私の中に生きている。